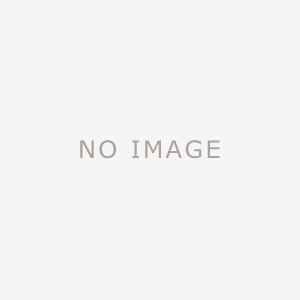再生医療・iPS細胞ニュース
新聞等に掲載された、iPS細胞に関する記事をご紹介します。
紹介記事一覧
【速報】ユニクロ創業・柳井会長が45億円寄付「iPS細胞」研究施設開所 培養を自動化、費用は50分の1に
「ユニクロ」を展開する「ファーストリテイリング」の柳井正会長兼社長が45億円を寄付して作られたiPS細胞の研究施設「Yanai my iPS製作所」が大阪市内に完成し、20日、開所式が行われました。患者自身の細胞から作った「iPS細胞」の培養を自動化し、費用をこれまでの50分の1に抑えるということです。
山中教授も出席「非常にチャレンジングなプロジェクト、良心的な価格で届ける」
20日午前11時から行われている開所式には、柳井正会長兼社長と京都大学iPS細胞研究財団の理事長を務める山中伸弥教授が出席しました。
柳井会長は「自分の血液からiPS細胞ができるのは画期的なこと。今からどんどん発展して、他の病気も治療にも役に立つという、夢が膨らむプロジェクトだと思っている」と述べました
また、山中教授は「非常にチャレンジングなプロジェクトだが、これからも患者に最適なiPS細胞技術を良心的な価格で届ける使命を達成するために精進していく」と話しました。
手作業の培養を自動化 5000万円→100万円に 拒絶反応の心配なし
大阪・中之島にできた最先端の研究施設「Yanai my iPS製作所」は、柳井会長が2021年度から毎年5億円を9年間、プロジェクトに寄付することを決め、3月に施設が竣工。5月に臨床用のiPS細胞の製造施設として近畿厚生局が認可しました。
この施設では、患者自身の細胞から「iPS細胞」を機械を使って自動で製造することができます。これまでiPS細胞は手作業で培養されていて、1つの細胞を製造するのに多数の人員が求められているほか、高度な無菌状態の作業所が必要で、製造期間は半年ほど、費用も約5000万円(1製造あたり)かかっています。
こういった課題を解決するため、研究所では、細胞の培養を自動化。製造にかかる人員を削減できるほか、1年に製造できる細胞数が1000個近くになるなど量産化でき、費用はこれまでの「50分の1」の100万円前後にまで抑えることができるようになるということです。
また現在は、健康で拒絶反応の少ないドナー由来の細胞からiPS細胞を作成し患者の治療に充てられていますが、患者によっては拒絶反応が出たり、難病の治療では使用できなかったりするなどの課題もあります。患者由来のⅰPS細胞では、そういった課題も解決できるになるということです。
山中教授らはⅰPS細胞を使った医療が多くの人に普及することを目指していて、人への臨床研究は2028年ごろになるということです。
【速報】ユニクロ創業・柳井会長が45億円寄付「iPS細胞」研究施設開所 培養を自動化、費用は50分の1に
出典:Yahooニュース
iPS細胞から「ミニ肝臓」 大阪大学、肝機能補助する人工臓器へ
大阪大学の武部貴則教授らの研究グループは、iPS細胞からヒトの肝臓の構造と機能を再現した肝臓の「オルガノイド(ミニ臓器)」を作製した。ヒトの体が肝臓の構造を形作るうえで重要な2つの物質を見つけ、細胞に加えてうまく分化させた。2〜3年後をめどに、体外から肝機能を補助する人工肝臓として臨床試験(治験)に入ることをめざす。
ヒトの肝臓は大きく分けて3つの層からなる構造をしており、層ごとに糖の産生や脂肪の分解、アンモニアの分解といった異なる機能を持つ。iPS細胞などの万能細胞からオルガノイドを作り、肝不全などの治療や創薬に生かす研究が進んでいるが、こうした肝臓の構造と機能を再現する方法は知られていなかった。
武部教授らは、これまでの研究から肝臓の構造を形作る重要な物質としてビタミンCとビリルビンを見いだした。iPS細胞を肝細胞に分化させて2つのグループに分け、片方にビリルビン、もう一方にビタミンCを加えた。ビリルビンは細胞の外から加え、ビタミンCは遺伝子改変により細胞自身が合成できるようにした。
ビリルビン、ビタミンCを加えたそれぞれの肝細胞を混ぜて培養すると、ヒトの肝臓とよく似た構造と機能を持つオルガノイドができた。これを複数個集め、肝不全の状態にしたマウスに移植したところ、生存率やアンモニアの分解能力などが向上したという。
今後はこのオルガノイドを大型化した人工肝臓を作って治験を実施し、肝不全などの治療法としてできるだけ早くの実用化をめざす。研究成果は英科学誌「ネイチャー」に掲載された。
iPS細胞から「ミニ肝臓」 大阪大学、肝機能補助する人工臓器へ
出典:日本経済新聞社
脊髄損傷にiPS細胞移植 慶応大、世界初の臨床研究
慶応大は14日、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から変化させた神経のもとになる細胞を脊髄損傷の患者に移植する臨床研究の1例目を昨年12月に実施したと発表した。iPS細胞を使った脊髄損傷の治療は世界初。患者の経過は「極めて順調」という。今後はリハビリをしながら1年かけて安全性や運動機能の改善状況を調べる。
臨床研究では、スポーツ中のけがや交通事故で運動の機能や感覚を失った負傷後2~4週の患者計4人に、iPS細胞から作った神経のもとになる細胞を損傷部位に注射で移植する計画。今回移植を受けた患者の性別、年齢、負傷からの具体的な期間は公表していない。
【イメージ】iPS細胞から作った免疫細胞、がん治療にも 昨年11月に治験開始
iPS免疫細胞で治験 卵巣がん患者へ初移植―京都大など
京都大iPS細胞研究所などの研究チームは11日、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から免疫細胞のナチュラルキラー(NK)細胞を作製し、卵巣がん患者に投与する臨床試験(治験)を始めたと発表した。9月に1例目の移植を実施し、国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)で治験を続けているという。
iPS実用化「心震える」 オリヅルセラピューティクスの野中社長
チームは、健康な人の血液から作ったiPS細胞に、「キメラ抗原受容体(CAR)」の遺伝子を入れて、がん細胞を攻撃するNK細胞に分化させた。治験は、2024年3月末までの間、患者6~18人を対象に1週間に1回、最大4回投与することを予定している。
同研究所の金子新教授は「(世界中の人に)NK細胞を出発として、いろんな種類の免疫細胞を届けられる第一歩として意義がある」と述べた。
iPS細胞由来の免疫細胞をめぐっては、千葉大と理化学研究所のチームが昨年、頭頸部(とうけいぶ)がんの患者に投与する治験を行っている。
iPS免疫細胞で治験 卵巣がん患者へ初移植―京都大など